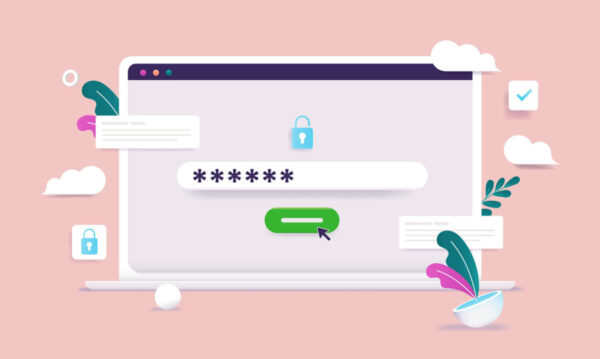この記事で解決できるお悩み
このような疑問に答えます。

ブログで初月5桁達成のこちゃです。
ぶっちゃけ、文章力がなくても収益化はできます◯
しかし、この記事を読めば、読者が求めている文章や、テクニックを知ることができます◎
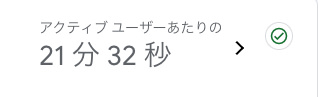
学んだことを実践することで、当サイトでは、読者の滞在率が増えています。
それでは、いきましょう!

ブログは「読みやすさ」「わかりやすさ」「欲しい情報」この3拍子が揃っていれば、読者は読んでくれます◎
- 難しい専門用語を使って説明する記事
- わかりやすい言葉で説明する記事
どちらが読みたくなるでしょうか?
後者の難しい言葉を使わずに、わかりやすい言葉で説明する記事ですよね?
わかりやすければ、情報がスイスイ頭の中に入っていくので、ストレスがかかりません。
「読みやす〜い!」って感じでどんどんスクロールします◎
しかし、難しいと「もういいや」となり、その先を読んでもらえません。
読者が必要としている情報を、「わかりやすい言葉で説明している記事」が求められています◎
友達に話しかけているイメージで記事を書くといいですね!

ブログの文章力がなくても、今から使える魔法を紹介します◎
それでは解説していきます。
1. まずは「型」をマネする(テンプレートを使う)
初心者が文章を書くときに最も大切なのは、「型」をマネすることです。
特に、読まれやすいブログ記事には「型」があります。
ブログ記事の基本構成(テンプレート)は下記です。
- 結論を書く(最初に答えを出す)
- 理由を説明する(なぜそうなるのか?)
- 具体例を入れる(実際の事例やデータ)
- 読者が実践できるアクションを示す(次に何をすればいいか)
- まとめ(もう一度要点を整理)
まずは「型」を意識して書くだけで、文章力がグッと上がります!
当サイトでも実践しています。
4,179回表示されたブログの書き方テンプレートの紹介!を真似れば、頭を悩ませることなく、流れが掴めるかなぁ〜と◎
2.体験談を必ず入れる
ブログ記事を読んでいると、「実際に使ってみた感想が知りたい!」と思ったことはありませんか?
ただの情報よりも、「リアルな体験談」があると、読者の信頼度がグッと上がります!
特に、アフィリエイトブログで商品を紹介するときは、体験談を入れることが超重要です◎
ブログに体験談を入れることで、次のようなメリットがあります。
- 体験談あり → 「この人、実際に使ったんだ!信用できる!」
- 体験談なし → 「本当に使ったことあるの?ただの宣伝じゃない?」
信頼される記事の違いを紹介します。
- ❌ 「このサプリはダイエットにおすすめです。」(ただの宣伝っぽい)
- ✅ 「このサプリを1ヶ月試したら、ウエストが3cm減りました!」(体験談があるとリアル)
体験談があると、読者が「この情報は本当なんだ!」と安心できます。
3.シンプルで分かりやすい文章を意識する
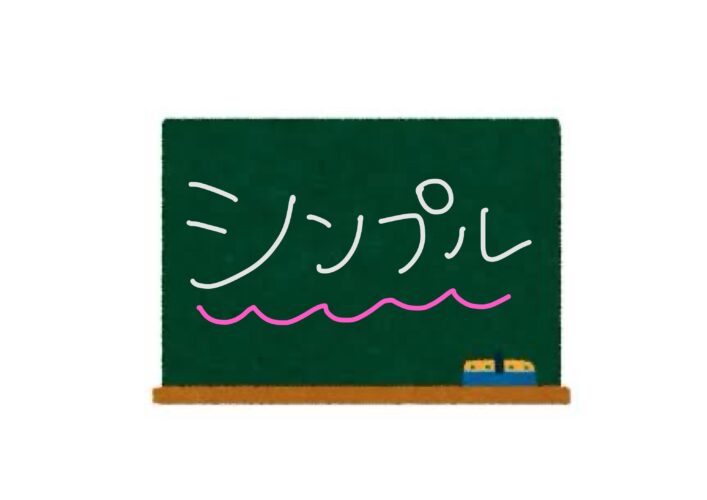
「分かりやすい文章=シンプルな文章」です。
いい例と、悪い例を比較して考えます。
悪い文章(長くて分かりにくい)
「ブログでアフィリエイトを成功させるためには、検索エンジンで上位表示を狙うことが大切ですが、そのためにはSEO対策をしっかり行い、適切なキーワードを選定し、さらに記事の構成を意識する必要があります。」
良い文章(シンプルで分かりやすい)
「アフィリエイトで成功するには、SEO対策が重要です。そのために、適切なキーワード選びと記事の構成を意識しましょう。」
1文を短くする(目安:1文40文字以内)ことで、スッキリした印象を与えることができますね◎
4.文章のリズムを意識して読みやすくする
単調な文章は読みにくく、最後まで読んでもらえません。
良い文章には 「リズム」 があります。
「リズムよく書くこと」が大事です◎
おすすめは、「短い文+長い文」を組み合わせること。
悪い例(リズムが悪い)
「ブログの文章はシンプルにしましょう。そして、分かりやすく書くことが大切です。また、SEO対策を意識してキーワードを入れましょう。」
良い例(リズムが良い)
「ブログの文章は、シンプルが大切。
分かりやすく書けば、読者に伝わりやすくなります。
さらに、SEO対策として適切なキーワードも入れてみましょう!」

リズムを意識すると、読みやすくなり、最後まで読んでもらいやすくなります!
5.書いた文章を声に出してみる
- 「ブログの文章がなんだか読みにくい…」
- 「もっとスムーズに伝わる文章を書きたい!」
そんなときにおすすめなのが、「書いた文章を声に出して読んでみる」こと!
だんまりして作った文章と、最後に声出しして確認した文章。
どちらが、リズム良い文章になったと思いますか?
声出しチェックをした文章です。
プロのライターやブロガーも実践しているこの方法を使うと、「読みにくい部分」「不自然な言い回し」がすぐに分かるようになります。
自分で書いた文章は 「ちゃんと読めているつもり」 になってしまいがちです。
声に出すと気づけることがたくさんあります。
- 1文が長すぎて息継ぎできない
- 難しい言葉や漢字が多すぎる
- 同じ単語が何度も出てくる
- 単調でつまらない文章になっている
- リズムが悪く、詰まる部分がある
- テンポよく読めない
読みにくい文章
「ブログの文章は、読者に伝わるように書くことが大切であり、そのためには、シンプルで分かりやすい言葉を使うことが求められるのですが、これを意識しないと、読者が途中で離脱してしまう可能性があります。」
声に出して改善すると…
「ブログの文章は、シンプルで分かりやすく書くことが大切です。
そうしないと、読者が途中で離脱してしまいます。」
声に出して読んでみると「ここ、長すぎる!」と気づくことができます。
6.毎日文章を書くことにトライ
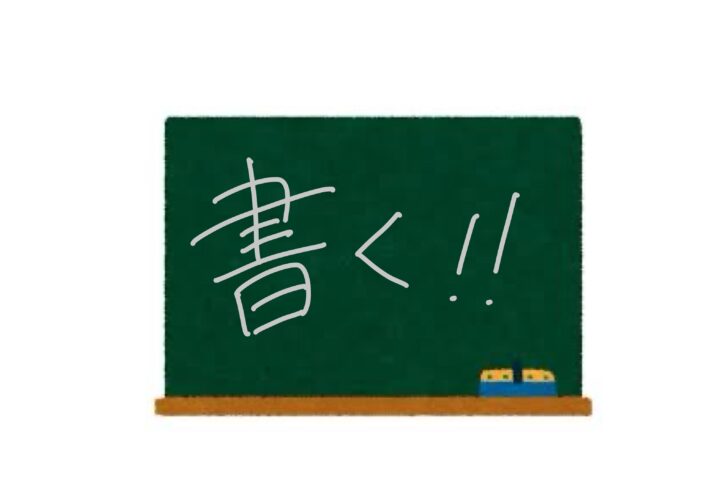
「早く1記事を完成させなさい!」と言っているわけではないです。
「毎日文章を書く習慣をつければ、自然と文章力が上がるよ!」ってことです。
インプットしてから、「ブログ書こう!」となると、作業ペースがどんどん落ちてしまいます。
だから、動きながら考えるというスタイルが一番おすすめできます。
私もそうしてきたからです。
「毎日書く習慣」をつけることで、文章力は確実に上達していきます。
当サイトで100記事書いた私が実践している書き方テンプレートを公開しています◎
4,179回表示されたブログの書き方テンプレートの紹介!から見れますよ〜
7.参考になるブログや本を読む
私は、本で学びながら、いいところを自分のブログに落としこんできました。
1つ学んだら、1つ取り入れる。
このやり方がインプットおばけにならなくていいので、おすすめできます◎
たくさんの本を読んできましたが、厳選して一冊に絞るなら下記の本になります。
8.「です・ます」表記を揃える
ブログの読みやすさを劇的に向上させる方法は、表記を揃えるということです。
ブログを書くとき、「です・ます」と「だ・である」が混ざっていませんか?
「ブログを書くときは、読者の立場に立つことが大切です。また、文章のリズムを意識すると、読みやすくなるだろう。」
なんだか違和感がありますよね。
「ブログを書くときは、読者の立場に立つことが大切です。また、文章のリズムを意識すると、読みやすくなります。」
このように、「です・ます調」と「だ・である調」が混ざると、文章が不自然に感じられ、読者にとって読みづらくなります!
「です・ます」を統一するメリットは3つあります。
- 読みやすくなる
- 読者の印象が良くなる
- 文章が洗練され、プロっぽくなる
「です・ます」を統一するメリット1つ目は、「読みやすくなる」です。
1.「読みやすくなる」
文章の語尾がバラバラだと、読んでいる人は違和感を覚えます。
一方、「です・ます」を統一すると、文章がスムーズになり、ストレスなく読めるようになります!
「です・ます」を統一するメリット2つ目は、「読者の印象が良くなる」です。
2.「読者の印象が良くなる」
文章の語尾が統一されていないと、「なんか読みにくいな…」と感じる読者が増え、途中で離脱してしまうことがあります。
一方、語尾を統一するだけで、プロっぽい文章になります!
- 「です・ます」調 → 柔らかく、親しみやすい印象
- 「だ・である」調 → 硬く、論文や解説記事向け
読者に合った表記を統一することで、ブログの印象が良くなります。
「です・ます」を統一するメリット3つ目は、「文章が洗練され、プロっぽくなる」です。
3.「文章が洗練され、プロっぽくなる」
ブログ初心者の人は、つい語尾をバラバラにしがちですが、プロのライターは、必ず表記を統一しています。
なぜなら、表記の統一=文章の品質が高い ということだからです!
- 統一されていない文章は、読み手に「雑な印象」を与える
- 統一された文章は、「読みやすくて分かりやすい!」と感じてもらえる
語尾を揃えるだけで、文章のレベルがグッと上がります。
9.同じ語尾にならないように工夫する

ブログを書いていると、「です」「ます」「だ」「~と思います」 ばかり繰り返してしまうことはありませんか?
「ブログの文章は、分かりやすく書くことが大切です。また、適切な言葉を選ぶことで、読者に伝わりやすくなります。さらに、シンプルな構成を意識することで、最後まで読んでもらえます。」
すべて 「です」「ます」 で終わっていて、単調でつまらなく感じます。
このように、語尾が同じパターンばかりだと、文章にリズムがなくなり、読者が飽きやすくなります!
読者の離脱率を防ぐためにできることは…同じ語尾を繰り返さない工夫です。
工夫をすると以下のようなメリットが起きます。
- 読みやすくなる!
- 読者が飽きずに最後まで読んでくれる
- プロっぽい文章に見える
語尾のバリエーションを増やすと、リズムが良くなり、スラスラ読める文章 になります。
「ブログの文章は、分かりやすく書くことが大切です。適切な言葉を選べば、読者にも伝わりやすくなるでしょう。さらに、シンプルな構成を意識すると、最後まで読んでもらいやすくなります。」
語尾を変えるだけで、リズムがよくなり、スムーズに読めます◎
ブログは、読者に「最後まで読んでもらうこと」が重要ですよね?
適度に語尾を変えることで、「次はどんな内容だろう?」と、読者の興味を引き続けることができます!
「です」「ます」ばかり の文章は、初心者っぽい印象を与えてしまいます。
語尾にバリエーションをつけるだけで、文章が洗練され、プロっぽく見える のも大きなメリットですね!
10.会話調や問いかけを適度に入れる
- 「ブログを読んでもらいたいのに、すぐに離脱されてしまう…」
- 「最後まで読んでもらうにはどうすればいいの?」
こんな悩みを持っているなら、会話調や問いかけを適度に入れることを意識してみましょう!
読者がブログを最後まで読んでくれるかどうかは、「文章のテンポ」と「親しみやすさ」がカギになります。
そこで効果的なのが、会話調や問いかけを使うことです◎
会話調や問いかけを入れるメリットは、3つです。
- 読者が「自分ごと」として考えやすくなる
- 文章にリズムが生まれ、飽きにくくなる
- 読者と「対話」している感覚を作れる
深掘りしていくと…
1.読者が「自分ごと」として考えやすくなる
問いかけを入れることで、読者は「これ、自分のことかも?」と、記事の内容を自分ごととして考えやすくなります。
問いかけがない文章(読者が受け身になる)
「ブログは継続することが大切です。しかし、続けるのは大変だと感じる人も多いでしょう。」
問いかけを入れた文章(読者が考えながら読む)
「ブログは継続することが大切です。でも、正直なところ、続けるのって大変じゃないですか?」
問いかけを入れると、「そうそう!そうなんだよね!」と共感を引き出しやすいです◎
2.文章にリズムが生まれ、飽きにくくなる
会話調や問いかけを入れるメリット2つ目は、「文章にリズムが生まれ、飽きにくくなる」です。
ずっと説明口調の文章が続くと、単調で退屈になりやすいです。
しかし、適度に会話調や問いかけを入れることで、リズムが生まれ、読者が飽きにくくなります!
説明ばかりの文章(単調でつまらない)
「アフィリエイトで稼ぐには、SEO対策が必要です。検索上位を狙うことで、多くの読者を集めることができます。」
会話調+問いかけを入れた文章(リズムがよく、読みやすい)
「アフィリエイトで稼ぐには、SEO対策が必須。でも、そもそもSEOって難しそう…と思いませんか?」
問いかけや会話調を入れるだけで、一気に親しみやすい文章になるんですよね♪
会話調や問いかけを入れるメリット3つ目は、読者と「対話」している感覚を作れる、です。
3.読者と「対話」している感覚を作れる
ブログは「書き手が読者に話しかけるような文章」にすると、読者は親近感を持ちやすくなります。
読者に話しかけるイメージで書くと、文章が自然になります。
- 「あなたはどう思いますか?」
- 「ちょっと想像してみてください!」
- 「こんな経験ありませんか?」
問いかけがない文章(他人事に感じる)
「ダイエットを成功させるには、食事管理が重要です。適切な食事を取ることで、体重が落ちやすくなります。」
問いかけを入れた文章(読者が自分ごととして考えられる)
「ダイエットって、結局のところ食事がカギ。でも、食事管理って難しいですよね?つい食べすぎてしまうこと、ありませんか?」
読者に語りかけることで、「自分のことだ!」と感じてもらいやすくなりますね◎
会話調や問いかけを入れるコツを3つ紹介します!
- 「あなた」や「〇〇していませんか?」を使う
- 適度に使う(1記事に2~3回)
- 読者が「イメージしやすい問いかけ」にする
会話調や問いかけを入れるコツ1つ目は、「あなた」や「〇〇していませんか?」を使う、です。
1.「あなた」や「〇〇していませんか?」を使う
読者が反応しやすくなる問いかけを使うと有効ですね〜
例えば
- 「ブログを書きたいけど、何から始めればいいか分からない…そんなことありませんか?」
読者に「そうそう!」と共感してもらえる問いかけを意識すればOKです◎
会話調や問いかけを入れるコツ2つ目は、「適度に使う」(見出し1に対して、2~3回)です。
2.「適度に使う」(見出し1に対して、2~3回)
考えて欲しいのですが、毎回「〜ですか?」という問いかけを使われても…
「いや、くどいんやけど…」って気持ちになります。
適度に入れることで、自然な流れを作っていきましょう!

文章量に応じて適宜調節したらいいですね♪
会話調や問いかけを入れるコツ3つ目は、読者が「イメージしやすい問いかけ」にする、です。
3.「イメージしやすい問いかけ」にする
問いかけを作るときは、読者が具体的に想像しやすい言葉を使うことが大切です。
抽象的な問いかけ(イメージしにくい)
「あなたはSEOを意識していますか?」
具体的な問いかけ(イメージしやすい)
「あなたは記事を書くとき、タイトルにキーワードを入れていますか?」
具体的に問いかけることが、読者に考えさせる機会を作り出します◎
11.箇条書きを使って、視覚的に読みやすくする
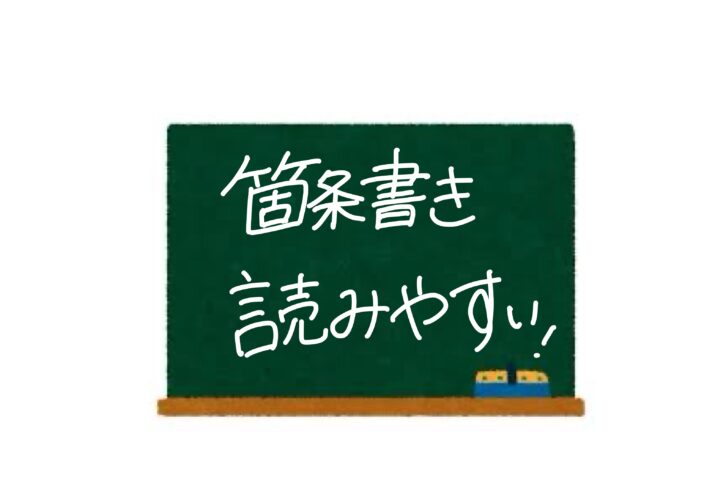
語尾を変えるのが難しい場合は、箇条書きを使うのも有効 です!
「ブログを続けるには、継続力が必要です。そして、毎日更新することが大切です。さらに、読者目線を意識することが重要です。」(単調)
ブログを続けるコツは、次の3つです。
・毎日書く習慣をつける
・SEOを意識する
・読者目線で文章を考える
箇条書きを使うと、自然に語尾が変わります◎
12.難しい漢字より、ひらがなを使う
- 「ブログの文章が、なんだか読みにくい…」
- 「読みやすい文章にするにはどうしたらいいの?」
そんなときに意識したいのが、「難しい漢字を減らし、ひらがなを適度に使うこと」 です!
漢字が多すぎると、読者は「むずかしそう…」と感じてしまい、読む気がなくなる こともあります。
一方で、適度にひらがなを使うことで、文章がスムーズに読めるようになります◎
どうして、難しい漢字を減らして、ひらがなを使うのでしょうか?
下記のようなメリットが3つあるからです。
- 読みやすくなる!
- 読者が疲れにくくなる
- 誰にでも伝わりやすくなる
難しい漢字を減らして、ひらがなを使うメリット1つ目は、「読みやすくなる」です。
1.「読みやすくなる」
ブログは「読むための文章」なので、パッと見てスムーズに読めることが大切 です。
しかし、難しい漢字や熟語が多すぎると、読者がつまずいてしまいます。
漢字が多すぎる文章(読みにくい)
「私が執筆した記事の内容は、読者に理解されやすいよう配慮を行いました。」
適度にひらがなを使った文章(読みやすい)
「私が書いた記事の内容は、読者にわかりやすいように工夫しました。」
漢字をひらがなにするだけで、スムーズに読めますね◎
難しい漢字を減らして、ひらがなを使うメリット2つ目は、「読者が疲れにくくなる」です。
2.「読者が疲れにくくなる」
文章の中に難しい漢字や熟語が続くと、読者は無意識のうちに疲れてしまいます。
「読みにくいな…」と感じると、すぐにページを閉じられてしまうことも!
読者の離脱率が上がると、グーグルから高評価をもらうことは難しくなることに…
ひらがなを適度に使うと
- 視覚的にやわらかい印象になる
- 目がスムーズに動き、読むスピードが上がる
- ストレスなく、最後まで読んでもらいやすくなる
最後まで読んでもらうために、漢字ばかりの文章を避けていきましょう◎
難しい漢字を減らして、ひらがなを使うメリット3つ目は、「誰にでも伝わりやすくなる」です。
3.「誰にでも伝わりやすくなる」
ブログの読者は、すべての人が難しい漢字をスラスラ読めるわけではありません!
特に、次のような人にも伝わりやすくするためには、ひらがなを増やすことが大切です。
- スマホで読む人(画面が小さいと漢字が読みづらい)
- 文章を読むことが得意ではない人
読者のことを考えるなら、「ひらがなを適度に使う」のが優しさですね◎
13.画像やブロック機能を使う
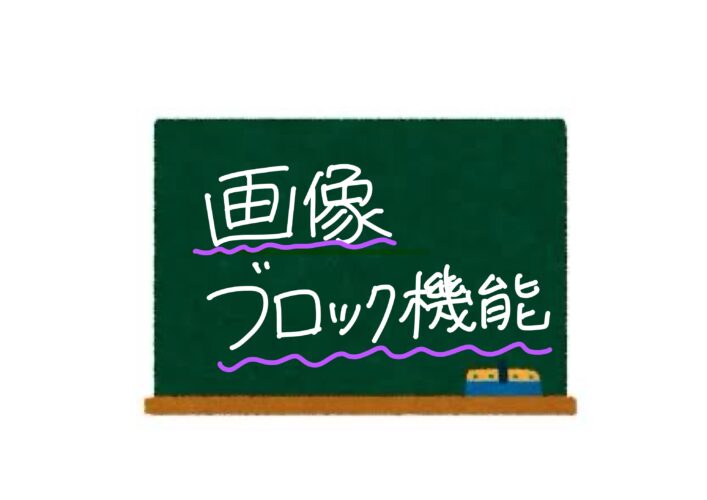
- 「文章だけのブログって、なんだか読みにくい…」
- 「もっと見やすく、わかりやすい記事にしたい!」
そんなときに活用したいのが、「画像」と「ブロック機能」 です!
ブログは、ただの文章の羅列ではなく、読者にとって「読みやすい・理解しやすい」構成が大切 です。
どうして画像やブロック機能を使った方がいいのか、3つ理由があります。
- 視覚的にわかりやすくなる
- 読みやすくなり、最後まで読まれやすくなる
- SEO対策にもなる
画像やブロック機能を使った方がいい1つ目の理由は、「視覚的にわかりやすくなる」から。
1.「視覚的にわかりやすくなる」
ブログ記事が文字ばかり だと、読者は疲れてしまいます。
しかし、適度に画像やブロック機能を使うと、視覚的にわかりやすくなり、理解しやすい記事 になります!
例えば…
- 「使い方を説明する記事」 → 実際の画面や操作画像を入れると、一目で理解できる
- 「おすすめ商品の紹介」 → 商品画像があると、読者の購入意欲が高まる
- 「旅行記やレストランレビュー」 → 画像を入れると、読者がイメージしやすい!
「読む」のではなく、「見て理解できる」記事が理想です◎
扱うジャンルによっては「え〜、そんなのむり〜」ってなるかもですが、できるだけ目指していこう!って感じでOK◎
画像やブロック機能を使った方がいい2つ目の理由は、「読みやすくなり、最後まで読まれやすくなる」から。
2.読みやすくなり、最後まで読まれやすくなる
長い文章がずっと続くと、読者は途中で飽きてしまいます。
そこで、画像やブロック機能を使って、適度に区切ることが大切に!
ブログに画像やブロック機能を入れることで…
- 文章が長く感じない(適度な区切りができる)
- 読者の目が疲れない!(流し読みでもポイントがわかる)
- 最後まで読んでもらいやすくなる
「読みやすい記事」は、「最後まで読まれる記事」になります!
画像やブロック機能を使った方がいい3つ目の理由は、「SEO対策にもなる」から。
3.SEO対策にもなる
Googleは、読者にとって「わかりやすい記事」を評価 するため、適切に画像やブロックを使うことでSEO効果もアップします。
SEOに効果的なポイントは
- 画像に「alt(代替テキスト)」を設定する(検索エンジンが画像の内容を理解しやすくなる)
- 見出し(H2・H3)を適切に使う(Googleが記事の構成を理解しやすくなる)
- 箇条書きやボックスを活用する(読者にとって読みやすい=SEOにプラス!)
画像やブロック機能を活用すると、検索順位アップも期待できます◎
14.専門用語は説明をつける
- 「ブログを書いているけど、専門用語が多くなりすぎていないかな?」
- 「専門用語を使うと、読者が離脱してしまうかも…」
そんな悩みを解決するのが、「専門用語には必ず説明をつける」 というルールです!
専門用語がたくさんあると、読者は「難しそう…」と感じて、記事を読むのをやめてしまうことも。
でも、適切に説明をつければ、初心者にも伝わりやすいブログ になります。
どうして専門用語には説明をつけた方がいいのでしょうか?
下記のように、3つのメリットがあるからです。
- 初心者でも理解しやすくなる
- 読者の離脱を防ぎ、最後まで読んでもらえる
- GoogleのSEO評価が上がる
専門用語に説明をつけるメリット1つ目は、「初心者でも理解しやすくなる」から。
1.初心者でも理解しやすくなる
読者は、必ずしもその分野の知識があるとは限りません!
例えば…
- 「SEO対策が重要です。」 → 「SEOって何?」
- 「アフィリエイトの成果発生にはCVが大事です。」 → 「CVって何?」
このように、専門用語を説明なしで使うと、初心者はついていけなくなり、読むのをやめてしまいます!
あなたも、そのような経験はありませんか?
いい例と悪い例を挙げてみますね。
専門用語を説明なしで使う(読みにくい)
「ブログのPVを増やすにはSEOが重要です。しかし、適切なキーワード選定と内部リンクの設計が必要です。」
専門用語に説明をつける(読みやすい)
「ブログのPV(ページビュー)を増やすには、SEO(検索エンジン最適化)が重要です。しかし、適切なキーワード選定と内部リンク(サイト内のページ同士をつなぐ仕組み)の設計が必要です。」
ちょっとした説明を加えるだけで、初心者でも理解しやすくなります◎
専門用語に説明をつけるメリット2つ目は、「読者の離脱を防ぎ、最後まで読んでもらえる」から。
2.読者の離脱を防ぎ、最後まで読んでもらえる
専門用語のせいで読者が「理解できない…」と感じると、すぐにページを閉じてしまいます。
読者が記事を最後まで読んでくれると…
- ブログの滞在時間が伸びて、SEOに良い影響が出る
- 読者の信頼を得て、他の記事も読んでもらいやすくなる
- アフィリエイト収益やクリック率も上がる
専門用語のせいで読者を逃さないように、わかりやすい説明をつけていきましょう◎
難しい言葉をわかりやすい言葉に置き換える手間が、あなたのファンを生む瞬間です!
- 「難しい言葉を使わずに教えてくれる!」
- 「わかりやすいから、この人が書いた他の記事も読みたい!」
同じキーワードで記事をたくさん書いている人がいたとしても、「あなたがいい!」そう言ってくれるのがファンです。
一手間かかりますが、読者がスイスイ理解できるように意識していきましょう◎
専門用語に説明をつけるメリット3つ目は、「GoogleのSEO評価が上がる」から。
3.GoogleのSEO評価が上がる
Googleは、「読者にとって役立つ記事か?」 を評価しています。
専門用語をそのまま使うより、わかりやすい説明がある記事のほうが評価されやすいです◎
Googleに評価される記事の特徴は
- 初心者でも理解できる言葉を使っている
- 難しい言葉には説明がついている
- 読者が「この記事はわかりやすい!」と感じて、最後まで読む
読者が理解しやすい記事を書くことで、SEO対策にもなりますね◎
15.主語と述語を近づける
- 「自分の文章が読みにくい気がする…」
- 「ブログを書いたけど、なんとなく伝わりにくい…」
こんな悩みを感じたことはありませんか?
文章が読みにくくなる原因のひとつに、「主語と述語が離れすぎている」 という問題があります。
主語と述語が離れると、読者は「何が言いたいのか?」を理解しづらくなります。
主語と述語は、文章の骨組み です。
- 主語(何についての話か)→ 「私は」「この本は」「ブログは」 など
- 述語(主語がどうなるのかを説明する部分)→ 「好きです」「面白いです」「大切です」 など
「このブログは、初心者にとってとてもわかりやすく、読みやすいので人気があります。」
上記で扱った文章の主語は 「このブログ」 で、述語は 「人気があります」 ですね!
主語と述語の関係が正しくつながっていると、文章がスムーズに読めます◎
主語と述語が離れると、どうして読みにくくなるんでしょうか?
主語と述語の間に長い修飾語(説明の言葉)が入ると、「主語は何だったっけ?」 と読者が混乱してしまうからです。
「このブログは、初心者にとってわかりやすい文章の書き方を学べるだけでなく、SEO対策やアフィリエイトの基本知識についても詳しく解説しており、多くの人に読まれています。」
主語(このブログ)と述語(読まれています)が遠すぎて、読みにくいんですよね…。
主語と述語を近づけるための2つのコツを紹介しますね◎
- 修飾語(説明の言葉)を入れすぎない
- 2つ以上の情報がある場合は、文を分ける
主語と述語を近づけるためのコツ1つ目は、「修飾語(説明の言葉)を入れすぎない」です。
1.修飾語(説明の言葉)を入れすぎない
長い説明が入ると、主語と述語が離れてしまいます。
できるだけシンプルにすることで、読みやすくなります!
悪い例(修飾語が長すぎる)
「このサービスは、ユーザーの満足度が高く、料金も手頃で、さらにサポートも充実しており、初心者でも安心して利用できるため、多くの人に使われています。」
良い例(主語と述語を近づける)
「このサービスは、多くの人に使われています。理由は、ユーザー満足度が高く、料金も手頃で、サポートが充実しているからです。」
一文に入れる情報を減らし、文章を短くすると読みやすくなります◎
主語と述語を近づけるためのコツ2つ目は、「2つ以上の情報がある場合は、文を分ける」です。
2.2つ以上の情報がある場合は、文を分ける
1つの文にいろいろな情報を詰め込むと、主語と述語が離れてしまいます。
そういうときは、文を2つに分けると、スッキリ伝わりやすくなります!
悪い例(長すぎて読みにくい)
「このアプリは、シンプルなデザインで使いやすく、初心者でもすぐに操作に慣れることができるので、ダウンロード数が増えています。」
良い例(文を分けてスッキリ!)
「このアプリは、シンプルなデザインで使いやすいです。初心者でもすぐに操作に慣れるため、ダウンロード数が増えています。」
1つの文が長くなりすぎたら、「文を2つに分けられないか?」を考えましょう◎
16.結論ファースト!

- 「ブログを書いたけど、なかなか最後まで読んでもらえない…」
- 「自分の文章、まわりくどくなっていないかな?」
そんな悩みを解決するのが、「結論ファースト」 という書き方です!
読者は、記事を読み始めた瞬間に「この内容は自分に役立つのか?」を判断しています。
結論を最初に伝えないと、読者は途中で離脱してしまう ことも。
結論を最初に書くと…
- 読者がすぐに「この記事は読むべきか?」と判断できる
- 「なるほど!」と興味を持って、続きを読んでもらいやすくなる
あなたのサイトに訪れた読者が、「この人が書いた記事、すぐ答えがある!」
いい意味で、読者の期待を裏切るって大事です◎
結論ファーストを続けた結果、読まれる滞在時間が増えました!
やらない手はないですよ◎
17.ラスト、スマホで最終チェック!
- 「ブログを書き終わった!でも、本当に読みやすいかな?」
- 「パソコンではキレイに見えるけど、スマホでどう見えるんだろう?」
そんなときに必ずやるべきなのが「スマホでの最終チェック」 です!
今や、ブログの読者の 約8割以上がスマホで記事を読んでいる と言われています。
そのため、パソコンだけで確認して公開すると、スマホで読みにくくなっていることに気づかないままになってしまうことも…
- 1文ごとに改行しているか
- 画像やボタンのサイズは適切か
- 読者の視線を意識したレイアウトになっているか
上記の3点を意識すれば、読みやすい記事が完成ですね♪

読者がブログの文章よりも求めている事を、下記にまとめてみました。
一つずつ解説します。
1.自分の体験があるか
やっぱり気になる。
「この人、ちゃんと商品を使ってレビューしているのかな?」って。
想像で書くのと、実際に使って書くのじゃ、記事のクオリティは格段にちがいますよね?
自分だったら、どんな記事が読みたいか?
オリジナルの体験がある記事を読みたいと思うものです◎
2.科学的根拠を基に説明しているか
ここに尽きるな、、、って感じですね。
科学的根拠があるのと、ないのとではちがいます。説得力が。
主観がある記事も大事。
そこに加えて、説得力のある論文だったり、サイトからの引用があれば強いですね◎
3.読者の悩みを言語化できているか
「この記事に答えあるかな〜?」って気持ちで、読者はスクロールをしています。
書き出し部分で、読者の悩みをはっきり言語化すると、「お!これは!!」とスイスイ読んでもらえることでしょう。
しかし、悩みに対して触れていなかったら?
「まぁ、いいや〜」で記事を閉じられます。
4.読者の悩みを解決しているか
「どうしたらいいの?」と困っている読者。
そこに対して、「こうしたらうまくいくよ!」と導く記事を書く。
ここが大切ですね◎
大切なことでも、いきなりあれもこれもするのは、きついです。
余裕が出てきてからでいいので、1つずつ取り入れてみてください◎
ブログを書く文章力を鍛えるに関連する質問
アフィリエイトの知識が身についた本を数冊厳選して紹介しています。
学んで本当によかったものだけを紹介しているので、あなたもぜひ手に取ってみてくださいね!
KIndleで読めるものばかりで、お手頃ですよ!
当サイトを運営する際に使っているツールを紹介します。
キーワード選定から、画像のツールまで幅広く解説しているので参考にしてくださいね!
【初心者向け】ブログアフィリエイトのおすすめ必須ツール14選から解説します。
もちろんです!
私は最初ケチって無駄な時間を過ごしてしまいました。
どうして有料にした方がいいかというと月間検索数というものがわかるからです。
このように、実際に検索されているキーワードに対して記事を書くことが鍵です!
ラッコキーワード有料【ライトプラン】の使い方・機能17こ紹介!から続きを読めます。
結論、どっちもいります。
質と量のバランスがSEOにも影響する理由について解説しているので、ブログに必要なのは質と量どっち?【ブログ量産に潜むワナとは】から続きをどうぞ!
早速、結論からいうと、ブログ記事に最適な文字数は書く内容によります。
記事の目的や読者のニーズによって、適切な文字数は変わります。
読まれるブログ記事の文字数知ってる?押さえたい4つのポイントから続きをどうぞ〜
セールスライティングとは、読者の心を動かし、商品購入や申し込みにつなげるための文章テクニック のこと。
売れる文章・セールスライティングの書き方5つ&具体例で解説から続きを読めます。
一部を紹介すると
- 1人が好き
- 自分のペースでお金を得たい
- デスクワークが好き
が挙げられます。
ブログアフィリエイトに向いていない人や、向いていないと勘違いしている人の特徴についても解説しています。
ブログアフィリエイトに向いている人13選・向いていない人7選とは?から続きを読めます。
いつもおつかれさまです!
あえて遊んだり休むという選択肢がある中、あなたは「ブログに挑戦する」という選択を選んだんです。
それって素敵すぎます。

私自身、ブログを半年休むこともあれば、数ヶ月更新しない日もありました。
1番は本当にブログをやめてしまうことだと思っているので、たくさん休んでリフレッシュしてくださいね!
ブログ疲れたら休んじゃおう!もう続けられないと感じた時の処方箋から続きを読めます。
ブログを継続できない理由を一部紹介します。
- まだ習慣化されていない
- 一日の中で、ブログを書く時間を確保していない
- 目先の利益しか見えていないから
このように、継続できない理由はさまざまです。
逆にどういう理由があるのかわかれば、本当の意味でブログをやめることはないんじゃないかと思います。

継続するためにできることを10こ紹介しているのでお役立てくださいね!
ブログの継続が難しいあなたへ【365日継続するコツ10こ】から詳しく読めます。
特化ブログと比べたら、雑記ブログの方が収益が下がります。
一概にいえませんが、グーグルの方針が変わり、専門性が高いサイトを支持するようになっています。
なので、初めは雑記から始めて徐々に特化にしていくスタイルがおすすめですね!
初心者必見!雑記ブログは稼げない?収益化できないを回避する方法3から続きを読めます。
当ブログは高速レンタルサーバー「ConoHa WING(コノハウィング)」を使っています!
サイトの表示速度が爆速になります♪
初心者でも10分で出来るワードプレスブログの始め方を解説しています。
下記の記事を見ながらすると楽ですよ◎
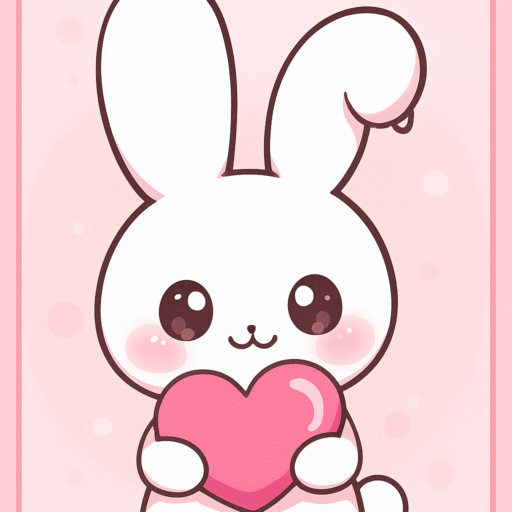 kocha głów blog
kocha głów blog