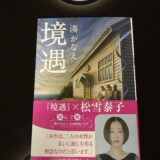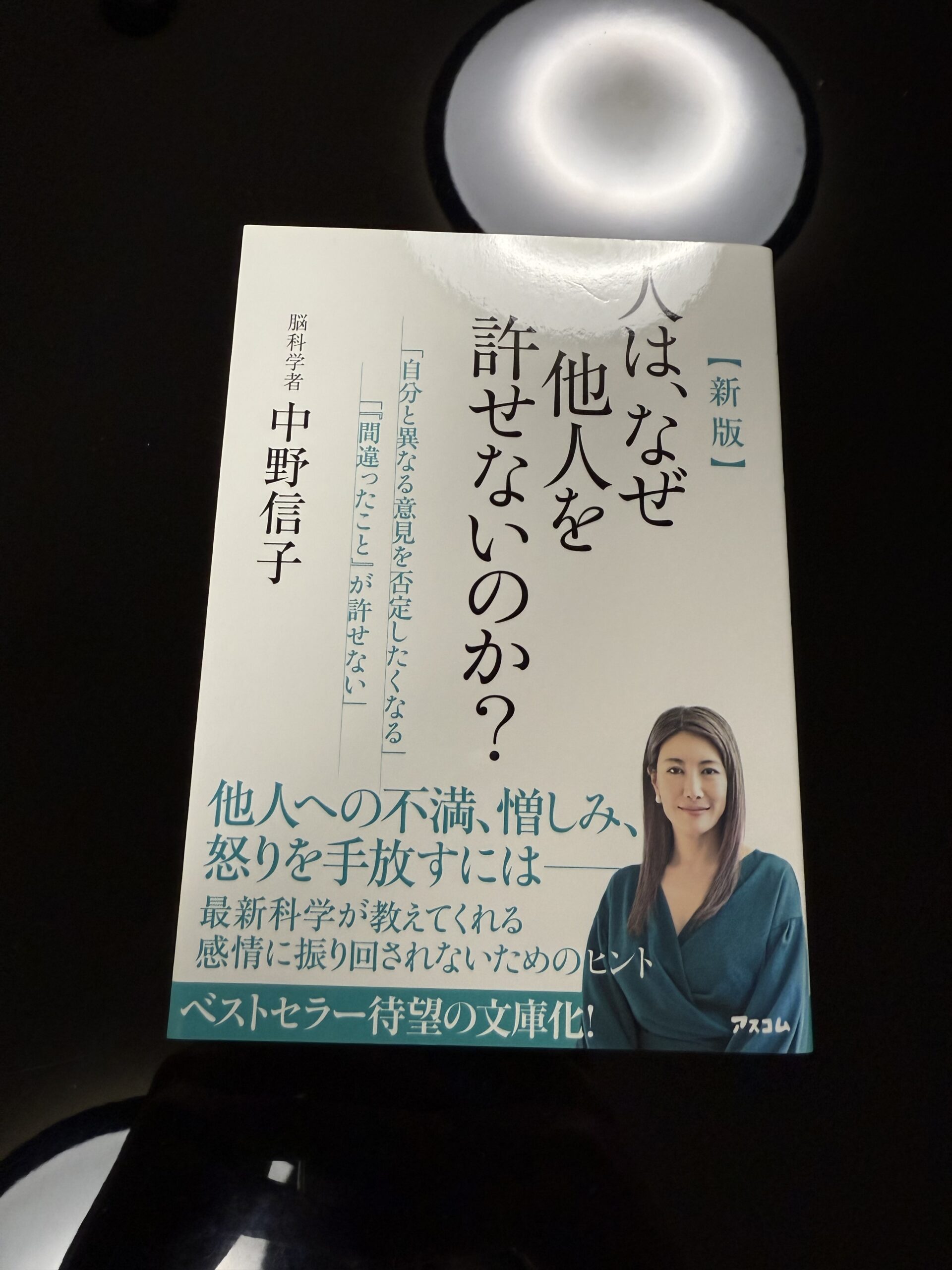この本は、こんなに人におすすめ♪
- どんな本を選べばいいのかわからない
- 知識が偏らない読書術とは?
- 人と長く付き合うための本の読み方とは?
上記の「移動する人はうまくいく」がベストセラーとなった背景について触れている。
彼は、デビュー9年目・11作目がベストセラー本になった。
本を読むという習慣を継続することに価値があるので、「私は読書をする人だ」というキャラクターをつくることが重要だと語っている。
これまで本を読まなかったからとか、過去によって自分のキャラが引きずられるのではなく、先にフリでもいいからキャラを作ることが大切だと。
AI時代に突入し、フェイクニュースは従来のニュースより70%も広く深く、早く拡散するという研究結果も出ている。
そういった時代だからこそ、読書をし、確証バイアスなどにハマるリスクを軽減することができる。
読解力がつき、思考をくりかえすことで自分の既存の考え方と得られた情報の差を比較することにも繋がる。
それは、自分の感情と向き合うことになるので、自分の価値観を言語化していることにもなる。
そうすることで、自己理解だけでなく、相手の大切にしている価値観にも理解を示す一助になるのではないか。
また、言語化能力が上がることで、自分の思いを詳細に表現する力もつく。
人は出会った5人の平均値になると言われている。
だから、誰と過ごすのかを選ぶことは賢い選択だなと思う。
それでは、誰を選べばいいのか…
答えは、新しい環境に連れて行ってくれる人である。
変化を恐れずに新しい環境に挑戦することで、少なからず同じ影響を受けるからだ。
著者は、変化を楽しむ人と過ごす時間を大切にすることを推奨している。
他にも、人間関係について、狭く深くよりも浅く広く関わることを勧めている。
理由は、変化が激しい社会で新しい情報や機会が得られるかは、ネットワークの広さと多様性が関わっているから。
読書に限った話でないが、人間関係においても異業種の友達とのつながりがあった方が、物事を多面的に見る力が養われる。
それが創造性だけでなく、問題解決能力の向上にも繋がると言える。
読書の仕方に関してもそうだが、最初から最後までじっくり読まなければいけないという規則はない。
スキミングと言って、自分に関係のある部分をつまみ食いすることを推奨している。
そうすることで、本を読むという行為そのもののハードルを下げることができるし、限られた時間で現在の自分にとって必要な情報を得ることができる。
読書をするにあたって、どうしても好きな作家さんやジャンルに偏る傾向があるが、多様なジャンルをバランスよく読むことを本書から学んだ。
8〜10のジャンルを年に2・3冊読むことで浅く広く各分野の理解を深めていきたいと思った。
異なる思考体系や概念間の接続が創造性を生み出し、人間関係にもプラスの影響を与えてくれることを認識できた。
また、1つのテーマについては関連本を5冊読むことでそれぞれの知見を統合し、メタ分析をすることができる。
「これから読書を楽しみたい」と思っている人にぴったりの本だと思った。
書店に限らず、オンラインショップでも溢れんばかりの情報に毎日さらされている。
その中から、自分を守ってくれる盾を作るための読書術は欠かせないように思う。
私自身、20代前半は全く読書をしていなかったが、自己啓発本にハマったのをきっかけに読書に沼っている。
楽しい読書法を本書から得られるので、ぜひあなたに手に取って欲しい。
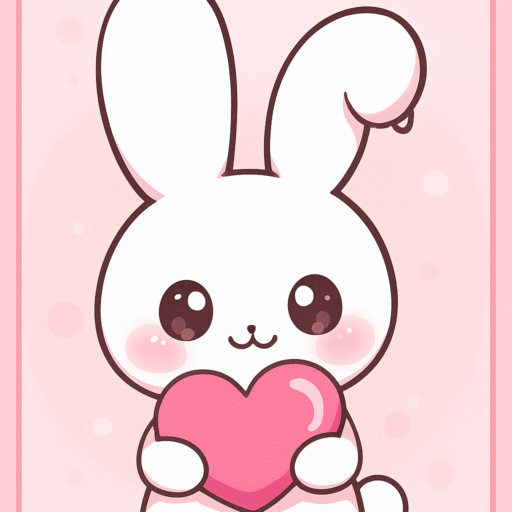 kocha głów blog
kocha głów blog